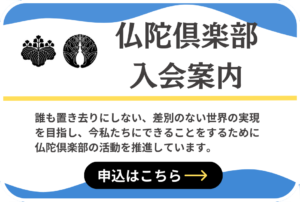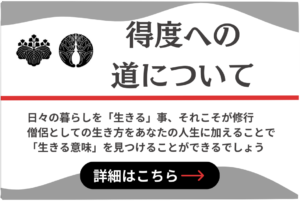大山の山肌に尽きることなく湧き出す湧水があり、 そこから清らかな流れが麓へと続いている。その一つの湧水で水筒、ペットボトルに水をいただいた。
地元の人も”ここの水はおいしい” と来ておられた。 八海山の麓を潤す水は、魚沼のお米と銘酒を育てた。
磐梯山の周りの湖、猪苗代湖 秋元湖などは、磐梯山の山水を源に、 その湧水やそこからの流れが火山爆発でせき止められたりして生まれたものである。 それらすべてが、その地の人々の暮らしの水として、風光の糧としてかけがいのないものとなっている。
私の村は、びわ湖からわずか数百メートルの地にあるのだが、飲み水も農耕水も不自由な村であった。 目の前に満々と湛えるびわ湖の水を眺めやりながら、それを取り入れる術を知らなかった。
びわ湖に流れる川の最下流にあり、水の不自由は当たり前とされていた。 どの家にも前栽があるが、 そこに池泉を設けることは互いの戒めとして避け、 限られた水を大切にしてきた。
江戸時代に、川上の村と水争いになり、 私の村の人が命を失い、以来その村とは縁を絶ち、今に至るも親戚関係はなく至っている。
その私の村にも、 田村山麓には地下水があり、 麓の家々は、 私の家も自家井戸があり、 今も生活用水の一つとして大切にしている。
山から離れた家は、 山麓の深井戸から竹樋で水を引き、 暮らしの水としてきた。 竹樋を同じくする家ごとに、「井組」 と呼ばれる組を作り、 毎年春に竹樋の掃除修築に努めてきた。
田村山麓の地下水は、村人の命の糧であった。 しかし、 小さな里山の田村に、山膚を流れる谷川はなく、 山に降った雨や雪をその小さな山体に、里人のいのちを支え続けてきた水を抱き続けてきたことを、私は知らなかった。
この秋の山旅は、四十代の怪我による足の障害で難しくなって以来、 およそ三十年ぶりであった。 どの山も頂に立つこは叶わなかったが、 前から後ろから妻に体ごと支えられながら、 山の素晴らしさに満たされた山旅だった。
大山 八海山、 磐梯山、 どの山にも数十メートルの河原のある雪や氷、雨で切り削られた渓谷、 わずか数十センチの川幅の小さな渓流が、 岩や木の根を洗い潜りいくつもの流れとなっていた。 手に掬い、 喉を潤し、 顔を浸し、その瀬音にゆっくりと体を休ませ、 “そうだったのだ、これなんだ!”と甲斐和里子さんの歌を思い起こさせていただいた。
いはもありこのねもあれどさらさらと
たださらさらとみづのながるゝ
山の谷水は、 そこに岩壁があろうが、 岩の原があろうが、 草木が茂り、無数の根が絡まった山膚であろうが、 自らが計らうことなく、窪地に溜まり溢れ、右に左に、 高きから低きへと、あるがままに、 ならしめられるがままに流れゆく。
甲斐和里子さんは、 「いはもありこのねもあれど」 に人の世の三毒五悪の無明を、 「さらさらとみづのながる」 に弥陀の本願の教えをお感じになったのではないだろうか。
磐梯山の十一月、登山道に入ってからのしばらくは重なる紅葉、中腹に近づくにつれひらひらと落葉の舞い、頂上は白く輝く霧氷、晩秋から初冬の山のすべてを見せてくれた。
谷川の水の流れに、 落ちた紅葉が一枚、一枚と浮かび踊りし流れてゆく。 澄み切った水面、 爽やかな水音に、赤や黄、茶色の鮮やかな色模様を描きつつ、 谷川沿いの幾重にも折り重なり、積もり積もった落ち葉
に別れを告げ、 流れ落ちてゆく。
一葉ずつおつるもみじをひとはづつ
ふもとにおくる山川のみず
甲斐和里子さんの歌である。
谷川を流れ下る落ち葉は、 浮きつ沈みつ小躍りしつつ流れゆく。 それは木の葉のときとは違った生き方の時を迎えているようにも思われる。 川岸ではなく川の水面に舞い散ったがゆえに与えられたかけがいのない再生なのではないだろうか。 甲斐和里子さんは、「一葉ずつおつるもみじ」 に老少不定、 独死を、 「ひとはづつ」 は、 弥陀のご縁をいただき、 水の流れの『願船』に乗せていただいた阿弥陀さまにお任せした人を、「ふもとにおくる」 は、 弥陀の清浄の地にお送りくださる、 「山川のみず」 は、 お念仏の白道をお教えいただいたのではないだろうかと私は思わせていただいた。
思いはあっても、 アルプスなどの山に登ることはもう無理であろうが、里山には登れるであろう。
山は誰もを拒むことはなく、”どうか、いつでも来ておくれ”と待っていてくれる。それは『一心正念直来』 のお喚び声ではないだろうか。