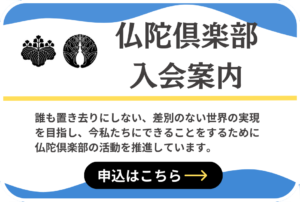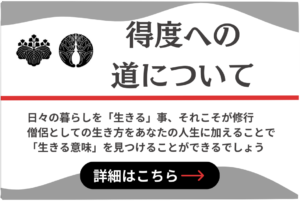二歳で母と死別、 大工であった父と三歳上の兄の三人、 差し金や鋸、 材木で叩かれ育った。
元々は百姓であったが、 明治の初め没落、 祖父はわずかに違った家屋敷、糧を大工に見つけた。
村の大工仕事は僅かな時代、 仕事を求め近在、京都にまで足を運んだ。
田舎にあって田畑はなし、 母のいない家庭は貧しかった。
父が還暦を迎えたころであったか、 夕餉のとき祖父の話になった。
「村の者から屑組の層と云われるほどの貧乏やったが、 親父の信心で男三人やってこれたなあ! 親父が子どもとき、 親が商売に手出し身上潰れたとき、 家にやあた立派な仏さんだけは、 借金の形にするのは勿体ないと大雲寺に預けたんや。
わしが子どものとき、 親父は兄貴とわしをようその阿弥陀さんに参りに連れてってくれた。
“阿弥陀さんに何でもお任せするんや。 と親父の口癖やったなあ!」と父。
その阿弥陀 (丈二尺余りの阿弥陀如来立像) さんは、縁あって戦後、戦災で失われた神戸市の浄土真宗福泉寺のご本尊としてご還寺された。
昭和二十一年十月三十一日付け、 福泉寺住職北野恵遵師から父宛の受領書が遺されている私も小学生の頃、父に連れられ何度か福泉寺にお参りさせていただいた。
父は弟であったことから大工職に見切りをつけ、 満州事変以降、戦争の拡大による兵員動員により職員不足となった旧国鉄に入った。
極貧の大工生活の家から自立し、 結婚した父の住まいは、 十坪ほどのトタン屋根の大工時代の木小屋であった。私は、昭和十九年十一月この木小屋で生まれた。
その年の暮れ、父は二度目の徴兵で朝鮮半島に出征、 終戦の年十月に帰還した。十畳一間、 敷きの小さな我が家にも、三尺の古びたお仏壇が置かれていた。
父や母に手を引かれ、 私も物心ついた頃には、お内仏の前に座り、 「なまんだぶつ」を称え、小学校に上がる頃には、 『正信偈』 は諳んじていた。
いつの頃からであったか、 お仏壇の前でだけ正座する父が不思議だった。
その不思議が、「真宗門徒、お念仏の父」 と知るのは、 ずっと後になってからである。
父の国鉄勤務は、 日曜日が休みとは限らなかったし、 夜勤もあった。
それでも大雲寺や多田幸寺の仏事に、 身が空けばお参りを欠かさなかった。
日曜日でぶらぶらしていると 「さあ、一緒に来い!」 と私を連れて行った。
大工仕事も出来たので、寺の造作や村人からの頼まれごとに大工箱を肩によくでかけていた。
特に思い出に残っていることは、村で亡くなられた方があると父が一手に・さんの最後の家やでな”と棺桶づくりを引き受けていたことである。
本当に丁寧に、 今もその父の声が聞こえてきそうである。
定年退職した父は、 翌年から東本願寺の同朋会運動に関わっていった。
貧しい家に育ち石瓦礫そのもであった過去、フイリピンで戦死した兄の無念、子どものころからのお念仏とのご縁、思うところがあったのであろうご本山に一週間、 十日と、 明石へ金沢へ福井へ名古屋へと足繁く、 それは八十歳ころまで続いたであろうか。
村においても、 大雲寺に同朋会を組織し今日に至っている。
亡くなった後、 遺されていた日記帳、 仏書を父の形見として相続している。
また多田幸寺の節分の豆撒きに、 年男として豆撒きをしたのは父が初めてで、 それは今に村人に継がれている。
平成十年、 母が亡くなった。 葬儀当日は葬列にいたが、翌日から中陰、年忌法要にも離れの寝所を離れなかった。
日々のお参りにも姿を見せなくなった。
母を人扱いしていないとさえ、時に思っていた父の寂しさ、 夫婦の絆を改めて考えさせられた。
そんなある日、「仏さんにお参りしたら」 と声をかけたとき、 「わしは此処でらせてもろとるんや!」 と、 そうだったのかと。
『何処でであろうと、どんな姿であろうと、そのまんま、 自分のできるようにお念仏申されよ』 法然上人のお言葉が浮かんだ。
平成十八年四月十四日、 満開の桜に包まれてお浄土へ、九十六歳であった。
最底辺の家庭に生まれ育ち九十六年を生きた父、幼いころからのお念仏に生ききったのだ、 凡夫としてのお念仏に。
その父のお念仏が、今私のお念仏にと。