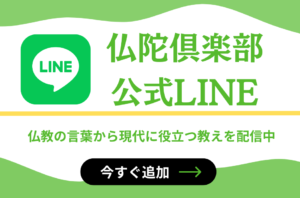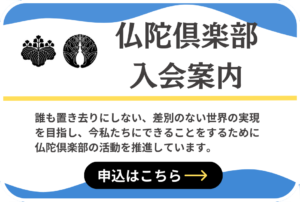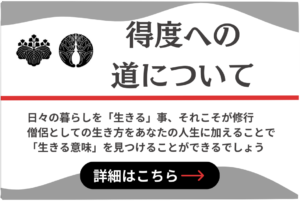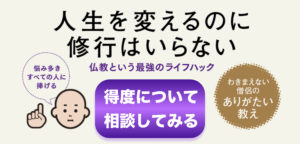自分が本当に求めているものを知るには
ボクは、親鸞の教えに出会い、死を意識して「今」を充実させるようになってから、 会う人にときおり「愛葉さんは、悟ってますね」と言われますが、自分でもおどろきます。
でもボクは、悟りの境地になどまったく……(笑)。
まだまだ欲だらけだとも言えますが、試行錯誤しながら、ここまでお話ししてきた、
「お金」「愛」「怒り」「嫉妬」「他人の評価」「見栄」を、少しずつでも手放す、または コントロールするようにしてきました。
人は生きているだけで、知らず知らずにいろいろなものをため込みます。
心にべったり貼りついた何かのせいで、仏教でいう「苦」(思い通りにならないこと)が生まれていることも少なくありません。
「でも、“執着”をすべて手放したら、“世捨て人”のようになってしまわない?」 と思う人もいるでしょう。
ボクは、「お金」「愛」「怒り」「嫉妬」「他人の評価」「見栄」をすべて手放すように オススメしているわけではありません。
どうやって少しずつ減らしながら、うまくコントロールしていくかをお伝えしたかったのです。
人が、モノやコト、そして人に執着してしまうほんとうの理由は、自分の気持ちを見ないようにするためです。
「仕事がデキないやつと、バカにされたくない」 「着飾らないと、まわりに埋もれてしまう」 などという気持ちに直接向き合うのがつらいため、「もっと成績を上げなければ」「どうにかすれば、もとの関係に戻れるかも?」「とにかくブランドのロゴが目立つものが欲しい」などという行動に走ります。
執着を減らすようにすると、最終的に見えてくるのは自分自身の心です。
そして、自分は何をほんとうに求めているのか、どうすれば幸せになれるかがクリアになります。
そして、確実に言えるのは、「お金」「愛」「怒り」「嫉妬」「他人の評価」「見栄」を、少しずつでもそぎ落としていくことで、悩みや苦しみを減らし、今をよりよく生きら れるようになるということです。
なぜボクがそう断言できるのか。 また、手放すものと手放さなくてもいいものの基準は何か。 その裏付けとなっている親鸞の教えについて、次でその特徴についてお話ししていきましょう。