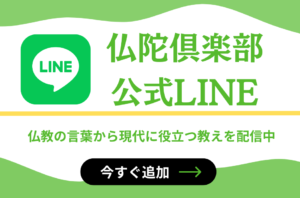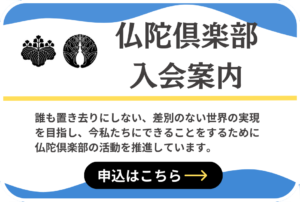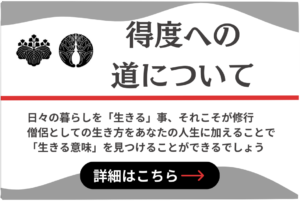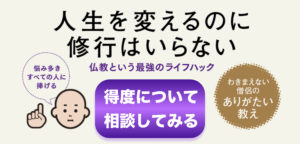仕事が思うようにいかない、人からイヤな態度をとられた、順番待ちが長くてイライラするなど「怒り」を感じる場面は、日常的にいろいろとあるでしょう。
「怒り」は、爆発させれば人間関係にヒビが入りますし、ぐっと飲み込んでもストレスがたまる。
怒りの対応は誰にとっても切実でしょう。「怒り」は、肉体的、そして精神的に「危険にさらされた」と感じると起こります。
たとえば、わき見をして走ってきた自転車にぶつかりそうになったら、自分の体が危険にさらされるわけですから「おい!!何やってるんだ」と怒りがわきます。
精神的には、自分を認めてくれない、ウソをつかれた、思い通りにいかないなど、 自身の存在が脅かされると怒りを感じるはずです。
「自分はもしかしたら、こんなところがダメなのかも?」と薄々感じていることがあり、誰かにそこを突かれたときに怒りを感じるのも同じ理由からでしょう。
でも仏教では、たとえどんなことが原因であれ、またどんなときでも「怒る」という行為は悪いと説いています。
「怒り」は、怒られた相手だけでなく、怒った本人にも毒のように悪影響を及ぼし、関わる人全員を不幸にするとまで言われているのです。
因果の道理(いんがのどうり)とは
仏教の基本を貫く思想に「因果の道理」があります。
これは、簡単に言うと「どんな結果にも、必ず原因がある。原因のない結果はあり得ない」ということです。
お釈迦様は「因果の道理」は、世の中の真実であり、すべてのものごとには原因と結果が必ずあると言っています。
つまり「怒り」が原因で生み出すものには、よい結果が生まれるはずがないということなのです。
ボクは20代の頃、いくつもの会社を経営していたとき、毎日のように社員を怒鳴り散らしていました。
思い通りに動いてくれない社員にイラ立ち、威圧的に攻撃してその場でいうことを聞かせようとしていたのです。今から考えると、怒っている自分もイヤな気持ちになり、さらにイライラが重なるばかり。
その場は丸く収まったように見えても、期待したようないい結果になることは結果的にありませんでした。